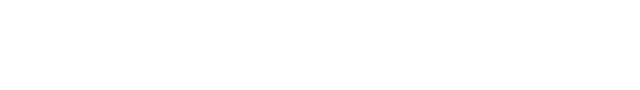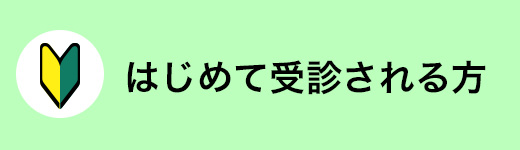高尿酸血症(痛風)の治療
高尿酸血症とは
尿酸値が7.0 mg/dLを超えた状態を高尿酸血症と呼びます。尿酸はプリン体という物質が分解されてできます。プリン体は食品に含まれる以外にエネルギー源として体内でも常に作られています。通常はプリン体が分解されてできる尿酸はうまく体の外へ尿などから排泄されるため血液中の尿酸値は適切な数値で維持されます。
高尿酸血症の原因として「遺伝要因」と「環境要因」があります。遺伝要因とは尿酸の体外への輸送に関わる遺伝子の変異により尿酸が尿から出ていきにくい(体に貯まりやすい)体質ということです。環境要因とはプリン体の多い食品の摂り過ぎやアルコールの飲みすぎ、肥満など日常生活に原因があるものをいいます。
高尿酸血症により起こること
①痛風
尿酸値といえば痛風です。尿酸が高い状態が続くと尿酸の結晶が関節内に沈着します。足の親指の付け根の関節によく起こりますが、足首や手首、肘の関節に起こることもよくあります。痛風の発作を起こしている期間は血液検査をしても尿酸値が普段より低くなることがあり、尿酸値が低いから痛風発作ではないとは限らないことに注意が必要です。
➁腎障害
高尿酸血症は慢性腎臓病の発症や進行に関連すると考えられています。
③尿路結石
尿酸値が高くなると酸性尿になることが多く尿路結石が出来やすくなります。結石が嵌頓(つまる)すると激しい疼痛を伴います。
④生活習慣病との関連
高尿酸血症は高血圧、糖尿病、脂質異常症などとともに、生活習慣病を合併しやすことが分かっています。
高尿酸血症の治療について
痛風の発作が起きている場合にはまずは痛風の治療を優先します。NSAIDと呼ばれる痛み止めや、グルココルチコイド(ステロイド)という炎症を抑える薬を使います。腫れている関節を冷やすと痛みが軽減させる効果があります。NSAIDやグルココルチコイドは副作用に注意が必要な薬であるため、使用はなるべく短期間におさえます。痛風発作中に薬で尿酸値を下げるとさらに発作を起こすことがあるため、まずは発作を抑える治療に専念し落ち着いたあとに尿酸値を下げる治療を行ないます。
尿酸値を下げる治療には生活改善とお薬の治療があります。生活ではまずは肥満に気を付けます。次に尿酸のもとであるプリン体の多い食品は摂り過ぎに気を付けましょう。
ビールはお酒のなかでもプリン体が多く痛風を起こしやすいことは聞いたことがあるかもしれません。実はビールだけではなくアルコール自体も摂り過ぎるとアルコールが体で代謝される過程でもともと体の中にあるプリン体が分解されて尿酸値が上昇します。ビールに限らず、アルコールの摂取自体をほどほどに抑えましょう。清涼飲料水に含まれる果糖も尿酸上昇に関与しますので飲み過ぎに気を付けましょう。
尿酸は尿から体の外へ出るため、お水をたくさん飲んで尿量を増やすと体内の尿酸も尿とともに排泄されやすくなります。1日2リットルの水分摂取を目指しましょう。ただし心臓や腎臓の悪い方は適切な水分摂取量が決まっていますので主治医の先生と相談してください。また水分はお水かお茶などにしましょう。甘いジュースや清涼飲料水はかえって尿酸値を上げる可能性があります。
痛風を起こした場合には再発の予防のために尿酸値を6.0未満に維持することが必要です。6.0未満を維持していけば関節のなかにくっついた尿酸の結晶がだんだん溶けていき、再発しなくなります。ただし痛風を起こした方は生活改善のみで6.0未満を維持することは難しいため、尿酸を下げるお薬を使うことがほとんどです。
尿酸の治療を始める場合、急激に尿酸値が下がると痛風を起こすことがあります。急激に尿酸値が下がると関節内に沈着している尿酸結晶の表面が変化したり、剥がれたりするため痛風が起きやすくなります。このためお薬を始める場合には少ない量から始めて、ゆっくり尿酸値を下げていくようにします。
尿酸値は高いが痛風は起こしたことがないという方(無症候性高尿酸血症)は、まずはしっかりと生活改善を行なうことが大事です。それでもなかなか尿酸値が下がらない場合にはお薬での治療も検討します。特に尿酸値が9.0以上の場合には、将来的に痛風を起こす可能性が高く、また高尿酸血症自体が高血圧や糖尿病、慢性腎臓病などの発症に関わるリスク因子と考えられています。
尿酸を下げる治療薬には尿酸生成抑制薬(体の中で尿酸が作られるのを抑える)と尿酸排泄促進薬(尿酸を体の外へ出すのを促す)があります。