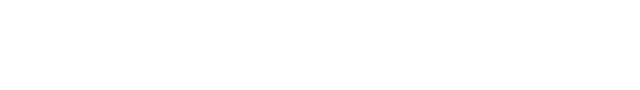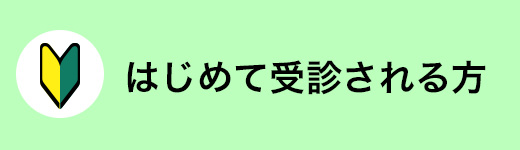高血圧の治療
高血圧管理・治療ガイドライン2025
高血圧と病気の関係
血圧が高ければ高いほど脳心血管病(脳卒中、心臓病)の発症率や死亡率が高くなります。腎臓の機能の低下や腎不全発症のリスクとも高血圧は関係します。日本における脳心血管病による死亡においては高血圧が一番の原因であるとされ、年間約10万人の方が高血圧が原因で亡くなっているとされています。
高血圧の診断について
病院やクリニックで測った血圧を「診察室血圧」、自宅で測った血圧を「家庭血圧」と呼びます。診察室血圧では上の血圧が140以上、あるいは下の血圧が90以上のいずれかどちらかでも当てはまれば高血圧と診断されます。ただし緊張や体調により血圧は変動しますので、1回のみでは判断せず、日にちの異なる2回以上の測定値で判断をします。家庭血圧の場合には上の血圧が135以上、あるいは下の血圧が85以上のいずれかどちらかでも当てはまれば高血圧と診断します。
高血圧の治療について
高血圧の治療には生活習慣の改善とお薬による治療があります。生活習慣の改善は全ての高血圧患者さんで行います。お薬での治療は患者さんによって開始する時期は異なります。すでに脳梗塞や心筋梗塞などにかかったことのある方、心房細動という不整脈のある方、糖尿病のある方、タンパク尿が出ていてる慢性腎臓病の方は高血圧による脳心血管病発生のリスクが高いため、生活習慣の改善だけでは高血圧が改善しない場合には早めにお薬での治療を行なうことを検討します。逆に65歳未満、タバコも吸わない、高血圧以外に持病がないなどリスクが低い方で血圧が140~150台くらいであれば、まずはじっくり生活習慣の改善を行なっていきます。
生活習慣の改善には減塩、節酒、運動、禁煙、食事内容の改善、肥満の改善などがあります。減塩は非薬物療法の基本です。食塩摂取は1日あたり6g未満を目指します。日本人における食塩摂取量は男性で11.0g、女性で9.3gと多いとされております。
野菜や果物に含まれているカリウムは塩分による血圧上昇作用を抑える働きがあり、積極的に摂取しましょう。ただし肥満や糖尿病のある方は果物の摂り過ぎは禁物ですので野菜をたくさん摂りましょう。
生活習慣の改善では血圧が十分下がらない場合にはお薬の治療を検討します。
高血圧治療の目標値について
75才未満の方、心筋梗塞や狭心症の治療中の方、タンパク尿陽性の慢性腎臓病の方、糖尿病の方などでは病院やクリニックの外来で測る場合には130/80未満、自宅で測る場合には125/75未満が目標です。75才以上の方、タンパク尿が陰性の慢性腎臓病の方などは外来での血圧は140/90未満、自宅での血圧は135/85未満が目標です。ただし血圧は下がり過ぎてもふらつなどの症状や内臓への障害が出る場合があり注意が必要です。
高血圧治療の意義
「一度飲み始めたら止めれらないので薬は飲みたくありません」とおっしゃる患者さんがときどきいらっしゃいます。お薬を飲み始めても、その間に減塩したり運動をしたり、体重が多い方はダイエットしたり、など生活改善を続けていくと途中でお薬を止められることもあります。もちろんなかなか止めることが難しい方もいらっしゃいます。しかし高血圧の治療の最大の目標はお薬を止めることではなく、血圧を最適に維持して脳梗塞や心筋梗塞などの病気を防ぐこと、最終的には健康で長生きすることです。