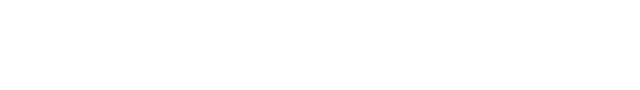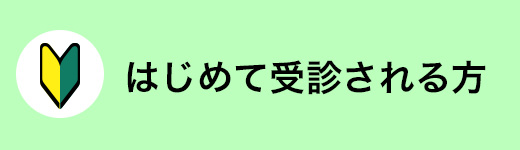認知症について
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー病とは、軽度認知障害(※1)や認知症(※2)の原因となる代表的な疾患で、初期にはもの忘れなどの記憶障害で気づかれることが多いですが、比較的若年の方の場合はもの忘れ以外の症状が目立つことも少なくありません。軽度認知障害や認知症の原因となる脳の病気はほかにもいろいろあり、また、からだの病気などでもよく似た症状がみられることがあります。さらに、認知症の進行や現れる症状はひとによって異なるので、的確な診断が必要です。
アルツハイマー病では、脳にアミロイドβと呼ばれるタンパク質がたまったり、リン酸化タウというタンパク質が塊を作って神経原線維変化と呼ばれる病変ができたりします。これらの病変の影響で神経細胞が障害され脳が萎縮していきます。近年このアミロイドβを標的とした治療薬の開発が進んできています(レカネマブ(レケンビⓇ点滴静注)もそのひとつです)。
※1 記憶障害などの軽度の認知機能障害が認められますが、日常生活にはあまり支障を来さない程度であるため、認知症とは診断されない状態を言います。
※2 アルツハイマー病などの病気により、認知機能障害(記憶、見当識、言語、計算、理解などの機能の低下)が認められ、日常生活に支障を来した状態を言います。脳の病気だけでなく、さまざまなからだの病気でも、よく似た症状が出ることがありますので、気になるときは、医師や地域包括支援センターなどに相談しましょう。
軽度認知障害(MCI)について
軽度認知障害は「脳の機能が健常な状態」と「認知症」の中間の段階で、MCI(Mild Cognitive Impairment)とも呼ばれます。記憶や判断などを行う脳の機能(認知機能)がいくらか低下しているものの、自立した日常生活を過ごせる状態を指します。MCIの状態からさらに認知機能が低下し、日常生活に支障をきたし介護が必要な状態になると、認知症と診断されます。
しかし、必ずしもMCIの人が認知症に進むわけではありません。MCIの原因によっては現状が保たれたり、回復したりすることもあります。